
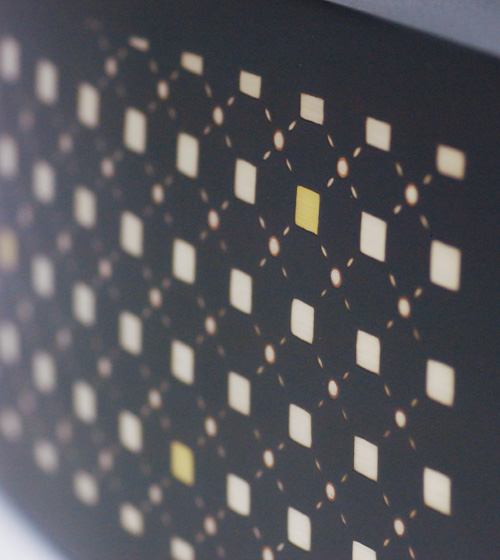
金属工芸の世界
金属は古くより「金・銀・銅・錫・鉄」の五種類が代表的なもので、これらは「五金」といわれ金属工芸の主要な材料として用いられてきました。たとえば硬く堅牢性にすぐれていることから、仏像や刀剣、甲冑などの武器の製造に用いられたり、熱伝導にすぐれ耐熱性が強いことから茶釜や鉄瓶として、そして叩くと音色を発することから鐘や鈴にも利用されています。また、金属が持つ独特の色彩や光沢を活かした、置物や花器、装身具など、美術工芸品の分野において、金属工芸ならではの美しい世界を築きあげています。
金属工芸の技法には、おおまかに、“彫ったり嵌めたりする「彫金」の技法”“板状の金属を立体に加工する技術「鍛金」の技法”“金属を溶かして造型された鋳型に流し込む「鋳金」の技法”があります。それらの技術によって、溶けたり延びたりといった金属個々の特性をうまく利用し、あらゆる金属製品が創りだされています。
